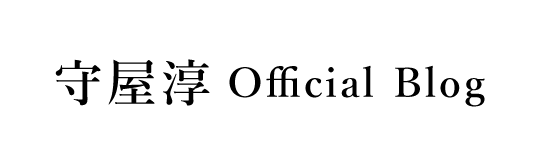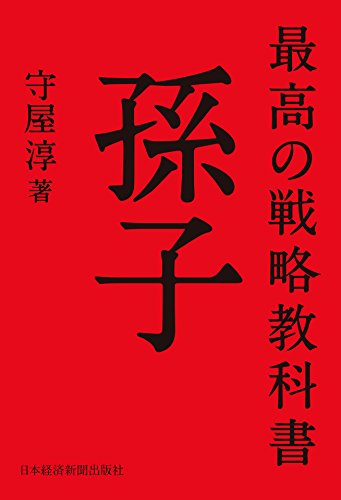第4回 限定情報から構成された全体像は、必ず間違える
筆者は、数ある学問のなかでも、経営学というのが結構好きなんです。
なぜかというと、文系の学問では珍しく、厳しい現実の審判を受けなければならない面を持っているから。要はビジネスの現場で成果上がらなければ、単なる空論にしかならないんですね。
これに対して、他の人文系のジャンルの場合——たとえば歴史学や哲学などでは、理論の検証の場があまりないため、平気で現実離れした持論が展開されたり、当事者の権力関係によって定説が決まってしまうことが往々にして起きてきます。要は、大家の主張するヘンテコな説と、若手の唱えたまともな説があったとして、権力の具合によって前者が主流になりかねない面も持っているんですね。
一方、経営学の場合、どんな大家がとなえた経営戦略やマネジメントの手法であっても、実際のビジネスの場で、
「現場ではゼンゼン使えないじゃん」
「頭でっかちも良いとこ。空理空論だ」
といった評価を受けてしまえば、「はい、サヨウナラ」にならざるを得ないわけです。もちろん、実際にはもう少しドロドロ——たとえば大家の唱える現実には使えない概念が、おべんちゃらのために学者内では使われ続ける——もあるようですが、傾向としては明らかに少ないといってよいでしょう。
そしてだからこそ、経営学というジャンルで生き残っている金言は、現実で活かせるモノが多いともいえるのです。筆者にとっては、その代表が表題にある、
「限定情報から構成された全体像は、必ず間違える」
ということ。
たとえば経営の場で、社長さんは、判断に必要な情報がすべてそろわないままに重要な決断をしなければならないケースが、ざらにあるわけです。こんな時、素晴らしい勘を発揮して、正確な判断をし続けられる人物なんて、ほとんどいないんですね。ですから、カリスマ経営学者だったドラッカーも、こういっているわけです。
《決して間違いや、へまや、失敗をしない人だけは信用できない。そのような人は、食わせ物か、それとも無難なこと、絶対確実なこと、とるにたりないことしか手をつけない人である》『マネジメント』ダイヤモンド社
《経営陣は、判断力に対して報酬を支払われているのであって、無過誤に対してではない。逆に、自らの過誤を認識しうる能力に対して、報酬を支払われているとさえいえるのである》『イノベーションと起業家精神』ダイヤモンド社
つまり、正しい全体像や見取り図など持ちようがなく、間違えざるを得ない状況というものを前提にして、いかに振舞うべきかを考えるのが、経営戦略でありマネジメントの技法である、とも言えるわけです。
で、ここから筆者の仕事に関連してくる話になるわけですが、この、
「限定情報から構成された全体像は、必ず間違える」
という教えは、筆者のかかわる歴史や古典解釈にもまさしく当てはまってくる面があります。
なぜなら、歴史も古典も、限定情報しか手元にないなかで常に全体像を探らざるを得ないから。だからこそ中国の古代史でいえば、新たな遺跡の発掘によって、それまでの定説がいくつもひっくり返ってきたわけです。また、古典の解釈においても、『論語』でいえば千を超える注釈が書かれてきたわけです。
裏を返せば、何が正しいかなんて——正しさというものが本当にあればの話ともいえますが——神のみぞ知る世界。大家同士が、立派な学説を戦わせているような状況があったとしても、数学的にいえば正しい確率35%と37%のものがドングリの背比べしているような話だったりするわけです。ちょっと極端な例に聞こえるかもしれませんが、確率70%の仮説を三つ乗っけてしまうと0.7 ×0.7× 0.7=0.343で、案外そんな程度になってしまうわけです。
もちろん、その2%の差が大切であると考えるのも重要なことですが、筆者としては、それならばその古典を、現代に生きるわれわれが活かしていく方向に使った方が、より実りがあるのではないか、と思ってしまったりもするわけです。もともと中国の古典——『論語』や『孫子』『老子』をはじめ、さまざまな歴史書に至るまで多くの作品は「使われること」を前提として書かれたものだったわけですから……
実は、こうした観点は20世紀を代表する文芸評論家・思想家のロラン・バルトの考え方に似ているかも、と筆者は感じたりもしています。要は、「テキストは読者のもの」ということなのです。
「本当にこれは本人(孔子、孫子、老子……)の残した言葉なのか」
「ねつ造ではないのか」
「そもそも、そんな人間本当にいたのか」
と疑い出したらきりがなくなる限定情報の塊としての古典——言葉をかえれば、確実なことは一つもないテキストにおいて、一つだけ確実なことは。
「そのテキストから、自分は楽しみを得た」
「そのテキストの教えを活かして、成果が挙げられた」
「自分が磨かれた」
つまり自分自身が、そこから何かを掴み取ったという事実だけなのです。この意味から、古典の解釈とは、それがどんなに奇抜に見えようと「本人が楽しめた」「腑に落ちた」「成果が上がった」というモノであればいい面を持っていると筆者は思っています。
もちろん、解釈の多様性を楽しむ余裕と、より腑に落ちた解釈があれば乗り換えられる柔軟性が保てれば、さらに理想的なのは言うまでもないのですが。